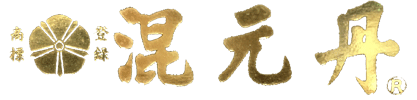加賀藩前田家の御用薬種商
金沢は小立野、寺町という二つの台地と犀川、浅野川という二つの流れを利用して作られた町といえる。
小立野台地の先端部に作られたのが、兼六園であり、金沢城である。
当時、金沢は尾山といわれ一向宗徒の居城であった。
1580年 (天正8年) 織田信長の武将柴田勝家が加賀に侵入し、配下の武将佐久間盛政が金沢御坊を落し入城した。
1583年 (天正11年)利家軍は賤ヶ岳の戦いに敗れた盛政軍を追い払い金沢城に入城した。
その後、利家は金沢城を居城とし、加越能三州を支配することとなり金沢の街作りに着手した。
中屋家の祖は山城の国の出身で戦乱のなか、落武者となって加賀の国・金沢の戸室山の麓に居を構え所司となっていた。
中屋家には代々伝えられていた混元丹という商品がありよく売れていた。
その他に医王山や近隣の野山で採れる薬草を販売する傍ら、代々伝えられてきた家伝薬の製造販売も始めた。
それ以来、代々が伝承を重ね寛文年間には前田綱紀公より前田家伝来の加賀三味薬といわれる紫雪、烏犀円、耆婆万病円の製造販売を許可された。
加賀藩へは各種の生薬を納入するなど、いわば、加賀藩前田家の御用薬種商であった。
時代の移り変わりを経て
江戸、明治、大正、昭和と商売は順調に推移し地域の信用も拡大した。
同時に生薬・薬種の販売も手掛けた。江戸時代には町奉行所から町年寄を拝命し、享保、宝暦、寛政と60数年に渡って務めた。
明治11年(1878年)10月、明治天皇の北陸巡幸が行われた。
岩倉具視以下随行員800人を伴い、新潟、魚津、富山を経て金沢に到着した。
金沢市内の中屋彦十郎宅に三泊宿泊されたが、このことは中屋家にとってはこの上ない名誉なことでした。
陛下は4日間滞在し石川県内の視察が行われたが、その目的は明治天皇の威光を人々に知らしめることだったといわれる。
陛下の行在所(あんざいしょ)は以外とこじんまりして質素であるが、威厳に満ちている。
現代に続く中屋混元丹
「混元丹煉り」は江戸時代の原料に限りなく近くするという精神のもとに、創業時の原典にのっとり胎盤(プラセンタ)を配合した。
原典に忠実に製造したということがいえる。
混元とは胎盤という意味であり、丹(タン)とは赤いということである。
つまり混元丹とは胎盤(プラセンタ)が含まれている赤いものということで、そのほかに高麗人参、黄精、クコシ、甘草、陳皮、山薬、ヨクイニン、エゾウコギ、ウコン、滑石、亜鉛、蜂蜜、青皮、橘皮、など20種類の原料を加え、代々の秘伝にこだわり厳格に製造した。
中屋家では近年は代々が彦十郎を襲名しているが、15代当主・彦十郎は「薬業通じて社会に貢献する」という先祖代々の精神を受け継ぎ、金沢を代表する名跡・混元丹を煉りとして発売している。
甘くて飲みやすくお茶をいただく前に舐めると金沢の歴史に思いを馳せることができるだけでなく、歴史都市・金沢の旅の記念にもなりぜひともお奨めしたい逸品である。
このほかに、丸薬状の「丸粒混元丹」、飴玉に混元丹成分を煉り込んだ固形の「混元丹飴」、歴史上の偉人・前田利家公の名前を冠した「前田利家公飴」も発売している。
2021.03